お知らせ・最新情報
【塾長日記】漢字検定対策 および漢検受験を悩んでいる方へ
こんにちは。塾長の林です。
別途ご案内しているように、
『2025年度第2回漢字検定のご案内【検定日10月25日(土)】』の受付を開始しました。
2025年度第2回漢字検定のご案内【検定日10月25日(土)】
多くの子どもさんに受験を検討して欲しいと思います。
しかし中には
「受験、面倒くさいな~…」とか、
「どんな勉強をすればいいのかわからない…」というお声・ご質問をよく聞きます。
今回は、そのように漢字検定に関して悩んでいる方へ、
私なりの考えと対策・選択を述べたいと思います。
・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・
【漢検対策について】
級によって出題内容が変わりますから、
一般的な勉強方法をお伝えします。
① 対策期間は「最低1ケ月」
漢字検定は当然ながら日本語表記なので、
英語検定よりも手軽さ・勉強のしやすさがあって受験する生徒もいます。
しかし、あまりにも「手軽=簡単」と考えてしまうために、
申込はしたけど、勉強はほとんどしていなかったり、
検定日の1週間前になって「過去問」をする程度になっている人が多数です。
当塾で受験する生徒さんのなかでも
とくに中学生はその傾向が強いです。
よって、残念ながら「不合格」になる割合も高くなります。
まずは、「対策期間は最低1ケ月」と決めて、
申込をした日から毎日(最低でも週4日)は勉強してください。
② 教材は「予想問題集」「分野別問題集」を
対策の勉強として「過去問」を使うことが多いです。
漢検WEBサイトでも「過去問」はあります。(無料で)
漢検に限らず英検や数検においても「過去問」を解くのは大切です。
しかし、WEBサイト上の「過去問」には「解説」がついていません。
なぜその答えになるのかの理由がわからないのです。
[例題1]
●次の熟語は、下のア~エのどれにあたるか、記号で答えなさい。
(漢検6級相当レベル[小5までの内容]問題)
(1) 絶食 (2) 大志
ア 反対・対になるもの (例…強弱)
イ 同じような意味になるもの (例…進行)
ウ 上の字が下の字の意味を説明しているもの (例…直線)
エ 下の字から上の字へ帰って読むもの (例…開会)
(1)の答えは「エ」です。「絶食」は「食を絶つ(食事をやめる)」という意味なので、下の字→上の字でよむと意味がわかります。
(2)の答えは「ウ」です。「大志」は「大きな志し(こころざし)」という意味なので、上の字→下の字でよむと意味がわかります。
このように、なぜその答えになるのかの理由を探り知ることがとても重要なので、「解説」が載っていなければミスしたときに理由がわかりません。
また、「過去問」は字のごとく過去出題された問題です。
傾向や問題レベル、時間配分などを知るには絶対必要ですが、
「過去問」はほとんど次の漢検では出題されません。
よって、出版社から刊行されている「予想問題集」を使えば「類題」が載っているので、
本番のような「初見問題」の対策ができます。
「分野別・大問別問題集」でもいいかと思います。
③ 順番的には「かき」「語彙」を優先
「合格=得点」であることは明白ですね。
しかし、配点の高い問題の正答率が低く、合格ラインに達しない生徒がとても多いです。
言い換えれば、下記のような配点の高い(やや難しい)問題を優先して解いてください。
●下線のカタカナを「漢字」になおす問題
[例題2]
授業のイッカンとして工場を見学する (3級レベル)
答えは「一環」です。(「一環」とはお互いに近い関係にありまたはつながっており、その一部であること)
●「四字熟語」を答える問題(5級から始まります)
[例題3]
晴コウ雨読の毎日をすごす (4級レベル)
答えは「耕」です。(「晴耕雨読」とは、田畑の広がるなかで生活をしている人がそのときの天候でのんびり有意義に生活するさま)
●「対義語・類義語」を答える問題(8級以上の問題で出題)
[例題4]
したのひらがなの中から選んで、それを漢字で書きなさい。
(類義語になおす問題)
展望 - ( )界
「し」「しゃく」「じゅん」「しき」「けい」
答えは「視(し)」です。(展望も視界も、自分の位置から「見える」眺め・範囲という意味)
他にもありますが、間違えたら「なぜ?」と疑問に持ち、辞典で調べることが大切です。
面倒くさがって周りの人に聞き過ぎると、脳内にインプットされないので、時間をかけた割には覚えていないということになります。
問題を解くよりも、『その答えの意味を探る』ほうが実はほんとうの漢検対策になるのです。
だから、どうしても一定期間の勉強が必要となります。
(これは「英語検定」も同様ですね。)
【漢検受験をお悩みの方へ】
「先生、今回わたしは受験したほうがいいですか?」
という質問・相談もよくあります。
「受ける」「受けない」の前に、
1つ『大前提』を理解しなければなりません。
「漢字検定」は漢字の知識量を試す試験です。
あたり前じゃん!と言われそうですが、多くの人が実際に理解していません。
漢検は本来、受験に必要な評定材料ではなく、日頃の漢字の知識量を確認・試すものです。
よって、
本来は漢検を申込む前から漢字の知識量を増やす勉強をしておかなければなりません。
この事前の(日ごろからの)勉強をしていない生徒が大半であるということです。
とは言え、いまから本気で受験を考えたいという方へアドバイスします。
① 受験を控える、おもに小6・中3の方へ
●検定日の2週間前~検定日までの間に「テスト」がある場合は受験しないほうがいいと思います。
優先順から考えて、受験に直結する勉強をすべきです。また、国語(漢字)以外にもしなければならない教科・単元もありますので、時間的にロスが多いです。
●しかし、一度も漢検・英検・数検を受験したことがない場合は、調査書等に記載する「特別活動」「検定などの実績」が白紙になる可能性があれば、該当級(もしくは1つ下の級)を受験し、確実に「合格」してください。そして調査書等の白紙を埋めておくといいでしょうね。
② 受験学年以外の小5以下、中1・2の方へ
●上記のように受験学年になると、受験勉強が中心になります。そのうえに漢検・英検の勉強が加わるととても大変です。とはいえ、現時点で合格できない級を受けても難しいです。
●よって、「来年苦労しないために、可能な限り受験して「級」を1つでも多く上げてください。すなわち、漢検・英検は受験学年に入る前の段階でどこまで「級」を取っておくかどうかが重要なのです。
③ 高校生の方へ
●実業系高校の生徒さんは可能であれば漢検チャレンジして、資格・検定の数を増やしましょう。(できれば準2級)
●普通科系高校の生徒さんの場合、大学入試を前提にしていると思います。ご存じのように大学入試では「英語検定」が重視されます。(ただこれについては多くの「誤解」もありますので詳細はご相談ください。)よって、漢検よりも英検を勉強・受験するようにしてください。(高2終わりまでに英検2級取得が目標)
④ 保護者の方へ
●できれば…ですが、お子さまと一緒に漢検受験してみてはどうでしょうか?お子さまよりも下の級でもかまいません。目的は保護者様の「自己啓発」「自己研鑽」の一環と捉えてもいいですが、親も頑張っていると子供も触発されることもあります。
今回は、「漢字検定対策 および漢検受験を悩んでいる方へ」と題して、私なりの考え・アドバイスを書きました。これを参考にして「漢字検定」受験、またはその他の検定受験をもう一度考えてみましょう。
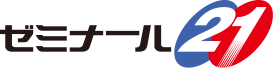
- 【集合授業形式】
- 楽しい授業の中にも、みんなで切磋琢磨し競い合って勉強しています。また、勉強や受験に対する心構えも教えていく、これが「ゼミナール21」スタイルです。

- 【個別授業形式】
- 「全教科学習できる個別指導」このコースのスローガンです。受験に必要な教科・科目、そして検定対策や思考力養成ができる、これが個別授業形式の「ソクラ」スタイルです。
ゼミナール21ソクラ国富校
電話 0985-41-8880 FAX 0985-41-8881
お電話でのお問い合わせ
ご希望の教室へのお電話は下の時間受け付けています。→ 教室情報
受付時間:月~土曜(15:00~21:00)